「スマホのブルーライトカットフィルムって、本当に意味があるの?」と疑問に思っていませんか。
目に優しい効果を期待して購入を検討する一方で、「効果がないなら、色味が変わるだけのフィルムは避けたい」と感じる方も多いでしょう。
この記事では、ブルーライトカットフィルムが「意味ない」と言われる理由を、日本眼科学会などの専門家の公式見解や最新の論文を交えて徹底的に解説します。
フィルムのデメリットや「逆に疲れる」と感じる原因、そしてフィルム以外の効果的な対策まで網羅的にご紹介します。
最後まで読めば、あなたがブルーライトカットフィルムを選ぶべきか、科学的根拠に基づいた最適な判断ができるようになります。
結論:「ブルーライトカットフィルムは意味ない」は本当?専門家の公式見解
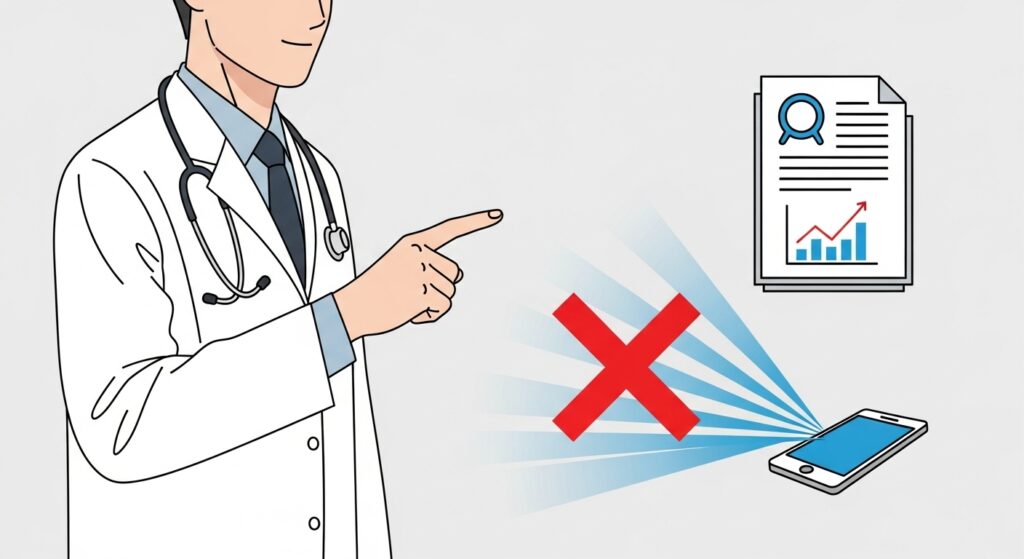
ブルーライトカットフィルムの効果については、国内外の専門機関から慎重な意見が示されており、「意味がない」あるいは「医学的根拠に乏しい」というのが現在の主要な見解です。
日本眼科学会などが「小児への装用は慎重に」と共同発表
日本では、日本眼科学会や日本眼科医会など6つの学協会が共同で「小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見」を発表しています。
この声明では、デジタル端末の使用が子どもの目に与える影響はブルーライトよりも、長時間の近距離作業や不適切な姿勢などが大きいと指摘しています。
さらに、太陽光に含まれるブルーライトは体内時計を整える重要な役割を持つため、過度にカットすることは発育に悪影響を及ぼす可能性も示唆しています。
米国眼科アカデミーも「目に損傷を与える科学的根拠はない」との見解
米国の眼科専門医が集う米国眼科アカデミー(AAO)も、デジタルデバイスから発せられるブルーライトが目に直接的な損傷を与えるという科学的証拠はない、との立場を示しています。
そのため、アメリカではブルーライトカット眼鏡の使用を一般的には推奨していません。
目の疲れやドライアイの原因は、画面を長時間見続けることによる「まばたきの減少」や「ピント調節の酷使」が主であると考えられています。
論文でも眼精疲労の軽減効果は証明されていない
2021年に学術誌『American Journal of Ophthalmology』に掲載されたランダム化比較試験では、ブルーライトカット機能を備えた眼鏡が、コンピューターを2時間使用した後の眼精疲労の症状を予防・改善する効果はない、と結論付けています。
また、2023年に発表されたコクラン共同計画のレビューでも、ブルーライトカットレンズが目の疲れを軽減するという短期的なメリットはない可能性が示唆されました。
なぜ「意味がない」「効果なし」と言われるようになったのか?
これらの専門機関の見解や研究結果が広く知られるようになったことが、「意味がない」と言われる大きな理由です。
デジタルデバイスから出るブルーライトの量は、太陽光に含まれる量に比べてごくわずかです。
そのため、眼精疲労や目の病気と直接結びつけるには根拠が不十分であり、ブルーライト対策よりも、適切な休憩や使用習慣の見直しの方が重要だと考えられています。
そもそもブルーライトとは?人体への本当の影響を解説

ブルーライトは、可視光線の中でも特に波長が短く、強いエネルギーを持つ青色の光のことです。
私たちの生活に密接に関わっており、良い影響と悪い影響の両側面を持っています。
ブルーライトの正体は?紫外線との違い
光には目に見える「可視光線」と、目に見えない紫外線や赤外線があります。
ブルーライトは、この可視光線の中で最も紫外線に近い380〜500nm(ナノメートル)の波長を持つ光です。
波長が短いほどエネルギーが強いという性質があり、空気中の粒子とぶつかって散乱しやすいため、まぶしさやチラつきの原因になることがあります。
【悪い影響】睡眠リズムの乱れや眼精疲労を引き起こす可能性
ブルーライトが人体に与える最も懸念される影響は、体内時計(サーカディアンリズム)の乱れです。
特に夜間にスマートフォンやPCから発せられるブルーライトを浴びると、脳が「昼間だ」と錯覚し、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されます。
これにより、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりする可能性があります。
また、光の散乱によるチラつきが、目のピント調節機能を疲れさせ、眼精疲労の一因になるとも言われています。
【良い影響】体内時計を整え、心身を活性化させる役割も
一方で、ブルーライトは健康維持に不可欠な役割も担っています。
日中に太陽光に含まれるブルーライトを浴びることで、私たちの体内時計はリセットされ、心と体が活性化します。
これにより、日中は活動的に過ごし、夜は自然な眠りにつくという健康的な生活リズムが保たれるのです。
ブルーライトを完全に悪者と捉えるのではなく、その性質を理解することが大切です。
問題はブルーライト自体より「浴びる時間帯」と「長時間の使用」
結論として、ブルーライト自体が絶対的な悪なのではありません。
問題となるのは、夜間に過剰に浴びることによる睡眠への影響や、デジタルデバイスを長時間連続して使用することによる目の酷使です。
ブルーライト対策を考える上では、単に光をカットするだけでなく、デバイスを使う時間帯や使い方そのものを見直す視点が重要になります。
ブルーライトカットフィルムのデメリットと「逆に疲れる」理由
ブルーライトカットフィルムは、目の負担軽減を期待して導入されることが多いですが、いくつかのデメリットも存在します。
場合によっては、かえって目の疲れを助長してしまう可能性も指摘されています。
デメリット①:画面の色味が変わる・黄色や青っぽく見える
最も大きなデメリットは、画面の表示色が変わってしまうことです。
ブルーライト(青色光)をカットするため、フィルムを貼った画面は全体的に黄色みや青みがかって見えます。
写真や動画の色合いが不自然になるため、正確な色彩表現を求めるデザイナーや、コンテンツを本来の色で楽しみたい方には不向きです。
デメリット②:屋外の太陽光下で画面が見えにくくなる
ブルーライトカットフィルムは、屋外の明るい場所で画面が見えにくくなることがあります。
フィルム自体が太陽光を反射して青く光ってしまい、ディスプレイの表示内容が判読しづらくなるのです。
画面の輝度を最大にしても見えにくい場合があり、屋外でスマートフォンを頻繁に利用する方にとってはストレスの原因となる可能性があります。
デメリット③:通常のフィルムより価格が高い傾向にある
ブルーライトカット機能が付加されている分、一般的な保護フィルムと比較して価格が高めに設定されていることが多いです。
効果の医学的根拠が明確でない点を考慮すると、コストパフォーマンスが良いとは言えないかもしれません。
なぜ「逆に疲れる」と感じる?レンズの反射光やゴースト現象が原因かも
一部のユーザーからは「ブルーライトカット製品を使うと逆に疲れる」という声が聞かれます。
これは特にメガネレンズで言われることが多い現象ですが、コーティングでブルーライトを「反射」させるタイプの製品が原因と考えられます。
レンズの裏面(目側)で室内の照明などが反射し、その光が目に入ることでチラつきやまぶしさを感じ、疲れにつながることがあります。
また、レンズ内で光が多重反射する「ゴースト現象」が、視界の違和感や疲れを引き起こす可能性も否定できません。
それでもフィルムを貼る?期待できる効果と利用者の口コミ

専門家からは慎重な意見が出ていますが、ブルーライトカットフィルムに全くメリットがないわけではありません。
使用者からは肯定的な声も多く聞かれ、心理的な安心感や副次的な効果も期待できます。
【効果】目のチラつき・まぶしさを軽減する効果は期待できる?
ブルーライトは波長が短く散乱しやすい性質を持つため、まぶしさや画面のチラつきの原因になるとされています。
ブルーライトカットフィルムを貼ることで、これらの刺激が緩和され、結果的に目の負担が軽くなったと感じる可能性はあります。
ただし、これは眼精疲労そのものを治療する医学的な効果ではなく、あくまで体感的な快適性の向上に近いものと捉えるのが適切です。
【効果】液晶画面の傷や破損から保護する本来の役割
ブルーライトカットフィルムも保護フィルムの一種であるため、スマートフォンの画面を傷や衝撃から守るという基本的な機能は備わっています。
どうせ保護フィルムを貼るのであれば、付加機能としてブルーライトカット効果のあるものを選ぶ、という考え方も一つの選択肢です。
【口コミ】知恵袋やSNSでは「目の疲れが楽になった」という声も多数
Yahoo!知恵袋やX(旧Twitter)などのSNSでは、「ブルーライトカットフィルムを貼ったら目の痛みが和らいだ」「明らかに目の疲れが軽減された」といった個人の体験談が数多く投稿されています。
科学的なエビデンスとは別に、プラセボ効果(思い込みによる効果)も含め、実際に効果を実感しているユーザーがいるのは事実です。
結局、ブルーライトカットフィルムは「気休め」や「お守り」なのか?
現在の科学的知見に基づけば、ブルーライトカットフィルムが眼精疲労や目の病気を防ぐという直接的な効果は限定的と言わざるを得ません。
しかし、まぶしさの軽減や、使用者の心理的な安心感につながる「お守り」のような役割は果たしているかもしれません。
明確な効果を期待するよりは、「少しでも快適になれば良い」という程度の気持ちで利用するのが現実的でしょう。
「カット率90%」は嘘?後悔しないフィルムの選び方
市場には様々なブルーライトカットフィルムが出回っており、特に「カット率」の数字が購入の決め手になりがちです。
しかし、この数字の表記には注意が必要であり、本当に自分に合った製品を選ぶためにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。
注意点:「最大90%」などカット率の数字に騙されないで
「ブルーライトカット率90%」といった高い数値を謳う製品がありますが、これは特定の波長の光(多くは紫外線に近い380nm付近)における最大値を示している場合がほとんどです。
ブルーライトの領域(380〜500nm)全体を平均して90%カットしているわけではありません。
もし本当に全域で90%もカットすれば、画面は真っ黄色になり、色彩が大きく損なわれてしまいます。
表記の数字だけを鵜呑みにせず、製品の仕様をよく確認することが重要です。
選び方のポイント①:カット率よりも透明度や画質の自然さで選ぶ
前述の通り、高いカット率は画面の黄ばみにつながります。
日常的な使いやすさを重視するなら、過度に高いカット率を求めるよりも、画面の色味を損なわない透明度の高いフィルムを選ぶのがおすすめです。
最近では、色味の変化を抑えつつブルーライトを低減するタイプの製品も登場しています。
選び方のポイント②:素材(強化ガラス/PET)と強度で選ぶ
保護フィルムとしての本来の性能も重要です。
素材には、透明度と強度に優れた「強化ガラス」タイプと、薄くて柔軟性のある「PET」タイプがあります。
傷や衝撃からの保護を最優先するなら強化ガラス、タッチ感度や薄さを重視するならPET素材が適しています。
おすすめはどれ?ブルーライトカット機能付き保護フィルムの比較
市場には多種多様な製品が存在するため、一概にどれが一番とは言えません。
エレコムやNIMASOといった有名メーカーの製品は、品質や性能に関する情報が多く、レビューも豊富なため参考にしやすいでしょう。
選ぶ際は、対応機種、カット率の表記方法、素材、透明度、価格などを総合的に比較検討することをおすすめします。
フィルムより効果的?今日からできるブルーライト対策
ブルーライトカットフィルムの購入を迷っているなら、まずはお金をかけずにできる対策から試してみるのが賢明です。
スマートフォンの設定変更や生活習慣の改善は、フィルム以上に効果的な場合があります。
対策①:iPhone・Androidの標準機能(Night Shiftなど)を活用する
ほとんどのスマートフォンには、ブルーライトを軽減する機能が標準で搭載されています。
iPhoneでは「Night Shift」、Androidでは「夜間モード」や「リラックスビュー」といった名称で設定できます。
これらの機能を使えば、指定した時間になると自動的に画面が暖かい色味に切り替わり、ブルーライトの発光を抑えることが可能です。
フィルムと違ってオン・オフが簡単にできるため、色味を正確に確認したい時だけ機能をオフにする、といった柔軟な使い方ができます。
対策②:画面の輝度(明るさ)を周囲の明るさに合わせる
画面が明るすぎると、目に入る光の総量が増え、目の負担が大きくなります。
特に暗い部屋で明るい画面を見るのは避けましょう。
スマートフォンの「明るさの自動調節」機能をオンにしておけば、周囲の環境光に合わせて画面の輝度が最適化されるため、目の疲れを軽減できます。
対策③:目の休憩「20-20-20ルール」を習慣にする
眼科医が推奨する簡単な休憩法が「20-20-20ルール」です。
これは「20分間デジタルデバイスを使ったら、20フィート(約6メートル)先を20秒間見る」というものです。
これにより、近くに固定されていた目のピント調節筋をリラックスさせ、眼精疲労を効果的に予防できます。
対策④:就寝1〜2時間前からスマホやPCの使用を控える
ブルーライトの最も大きな影響は睡眠リズムの乱れです。
これを防ぐ最も確実な方法は、寝る前のデジタルデバイス使用を控えることです。
特に就寝前の1〜2時間は、脳がリラックスしてスムーズに入眠できるよう、スマートフォンやPCから離れて過ごす習慣をつけましょう。
ブルーライトカットフィルムに関するよくある質問
ここでは、ブルーライトカットフィルムについて多くの人が抱く疑問に、Q&A形式でお答えします。
大人や子どもへの影響に違いはありますか?
子どもの目は水晶体が透明で、大人よりも多くの光を通しやすいとされています。
また、成長過程にあるため、体内時計の乱れなどの影響を受けやすい可能性があります。
そのため、日本眼科学会などは特に小児へのブルーライトカット製品の使用に慎重な姿勢を示しています。
対策としては、製品に頼る前に、まずデバイスの使用時間を制限し、適切な休憩を取らせることが最も重要です。
ブルーライトカットフィルムとスマホ本体の機能、どちらが効果的ですか?
ブルーライトを軽減するという点では、どちらも有効です。
フィルムは一度貼れば常に効果を発揮し、画面保護も兼ねるメリットがあります。
一方、スマホ本体の機能は無料で利用でき、手軽にオン・オフを切り替えられるのが最大の利点です。
コストや利便性、色の変化の許容度などを考慮し、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。
併用することも可能ですが、画面がかなり黄色っぽくなる可能性があります。
ブルーライトを完全に遮断する方法はありますか?
現在の技術で、可視光線であるブルーライトを「見え方を保ったまま」完全に遮断することは困難です。
カット率を上げれば上げるほど、画面の色味は大きく損なわれます。
現実的な対策は、遮断を目指すのではなく、デバイスの使用時間を管理したり、適切な休憩を取ったりすることで、ブルーライトとの付き合い方を工夫することです。
まとめ:ブルーライトカットフィルムは意味ないのか最終結論
ブルーライトカットフィルムが「意味ない」とされる背景には、眼精疲労や目の病気に対する直接的な保護効果の科学的根拠が乏しいという事実があります。
しかし、個人の体感としてまぶしさの軽減を感じる場合や、心理的な安心感を得るという側面も無視できません。
最終的には、専門家の意見やデメリットを理解した上で、自分にとって必要かどうかを判断することが重要です。
フィルムだけに頼るのではなく、スマートフォンの設定や使用習慣を見直すことが、最も効果的で本質的な対策と言えるでしょう。
- ブルーライトカットの効果は、日本眼科学会など専門機関からは懐疑的な意見が出ている
- 米国眼科アカデミーも、ブルーライトが目に損傷を与える科学的根拠はないとの見解である
- 眼精疲労の原因はブルーライトよりも、長時間の近見作業やまばたきの減少が大きい
- ブルーライトの悪影響として最も懸念されるのは、夜間に浴びることによる睡眠リズムの乱れである
- 日中に浴びるブルーライトは、体内時計を整える良い役割も持っている
- フィルムのデメリットには、画面の色味の変化、屋外での視認性低下、価格の高さがある
- 「カット率90%」などの高い数値は、特定の波長における最大値であり、平均値ではない点に注意が必要である
- フィルムを選ぶ際は、カット率よりも透明度や画質の自然さを優先するのがおすすめである
- フィルムより効果的な対策として、スマホのNight Shift機能や適切な休憩(20-20-20ルール)がある
- 最終的には、科学的根拠と個人の体感を天秤にかけ、自分自身で必要性を判断することが求められる
